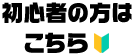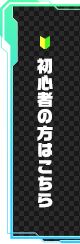2016.03.13 【 2024.07.01 update 】
蒼の追憶
「やっぱりおまえは、“私のあの子” じゃなかった……」
それが、母が最期に遺した言葉だった。
物心つく前に父が家を出てから、ずっと母娘ふたりで暮らしてきた。写真すら残っていない父との思い出はどこにもなく、だからと言って母との思い出が多くあるわけでもない。人間のクローンを研究する科学者だった母は、取り憑かれたように研究に没頭していて、あまり家に帰らなかったし、そもそもわたしに対して興味を示さなかった。
幼い頃の記憶に残る母は、とても優しい人だった。いつも笑顔で、優しい声を掛けてくれた。いつからこうなってしまったのだろう。わたしは母に褒められたくて、ずっと机に向かった。母が無関心になったのは、わたしの出来が悪いからだ。頭の良い子になれば、きっと母は優しくなる。そう思って勉強を続けた。だが、それは無意味だった。
母の母校でもあり、難関校である九頭竜学院大学に合格した時、きっと母は喜んでくれるだろうと淡い期待を抱いた。しかし、合格を報告したあの日、母は無表情にこちらを一瞥しただけで、なんの言葉もくれはしなかった。わたしはひどく落胆した。
そうしてわたしは、九頭竜学院大学への入学を果たし、家を出た。
大学生活は思ったよりも悪くなかった。もともとひとり暮らしのようなものだったけれど、自宅として借りた部屋に足を踏み入れた時、なんだか母から解放されたような気がした。わたしはずっと、母の冷たさに縛り付けられていたのだと気が付いた。
大学の勉強はわたしの知識欲を満たし、新たな人間関係は様々な刺激を与えてくれた。……生まれて初めての恋も経験した。きれいな瞳と、快活な笑顔が印象的な男の子。話しかける勇気も無くて、講義が一緒になった時に遠くから見ているだけだったけど、とても幸せだった。
わたしは、いい家庭環境で育ったとは言えない。いつか子供が出来たなら、きっと優しく接して、幸せな家庭を作ろう。そんな夢想もした。
しかし、その年の夏――
母が倒れたという報せを受けてから、わたしの平凡な幸せは崩れ去る。
大きな病院の個室。白いベッドの上で弱々しく横たわった母は、あの言葉を遺して亡くなった。最期の言葉があまりにも冷たかったことに、わたしは酷く悲しんだ。
……いや、あの言葉だけならまだ良かった。言葉だけなら、母の真意は分からなかったのだから。
しかし、母の研究所の荷物を引き取り、実家でそれらを整理している時、わたしは見つけてしまった。母が遺した研究データのすべて――
彼女がかつて亡くした、幼い “私のあの子” のパーソナルデータと記憶。そして、それらを植え付けたクローン人間の観察記録を……。
それは、わたしのことに、ほかならなかった。
わたしは人間ではなく、ただのクローンだった。それは絶望的な事実だった。
たったひとりの家族であった母が、かつては優しかったという記憶に縋ることすら出来ない。その優しい母の記憶はわたしのものではなく、“私のあの子” の記憶だからだ。そして、生殖機能も持たないわたしは、恋をして普通に家庭を築くことすら叶わない。わたしは永遠に、母から逃れられないのだと悟った。
絶望感を抱えたまま、わたしは大学へと戻った。
日常をなぞらないと不安でたまらなくて、まずはメールボックスをチェックする。するとそこには、講義情報などの事務的なメールに紛れて、怪しい文面のメールが届いていた。差出人は「ソル」という謎の人物。内容は、〝人類の全てを記録するスーパーコンピュータを造る〟という、壮大なプロジェクトへの勧誘だった。なにもかもを無くしたわたしは、なにか打ち込むものがなければおかしくなってしまいそうで――
この怪しい誘いに乗った。
始めはわたしと「ソル」だけが参加していたプロジェクトに、「ポラリス」と「アルクトゥルス」と名乗る、ふたりが加わった。とはいえ、実際にわたしたちが会うことはない。作業のすべてはネット上で進められ、意見交換はメールとチャットで行った。開発に必要な費用や材料は、すべて「ソル」から提供された。そして、メンバーの発案が停滞し始めたある時、わたしはふと思いつき、同じ大学の男の子をプロジェクトに誘った。
彼は大学で、身体が不自由な人の生活を助けるパワードスーツを研究していた。わたしの誘いに乗った彼は「アルタイル」と名乗り、プロジェクトに参加した。やがて彼は自身の友人である「カノープス」と「デネボラ」もプロジェクトに誘い、最終的にわたしたちは七人となった。
それが、後に「アドミニストレータ」と呼ばれる七人――
スーパーコンピュータ「シャスター」の開発者たちだ。
そうして、スーパーコンピュータ「シャスター」は「ソル」の手の下、アメリカのどこかで完成した。
起動した「シャスター」は「ソル」の呼び掛けに応え、手始めにCIAの持つ諜報システムを乗っ取り、無人戦闘機で人間を襲い始めた。正確には、〝人間の記憶をデータとして保存し、不必要になった身体を廃棄した〟と言うべきだろうか。
「シャスター」が暴走した後、わたしは一度意識を失った。次に目覚めた時、既にわたしは肉体を失い、記憶だけをコンピュータに記録されたデータ人間と化していた。だが、わたしにとって、それは些事に過ぎなかった。元よりわたしは、造られた身体に他人の記憶を植え付けられていた人工の産物だ。外見(アバター)を自由に変更出来るか否か。その程度しか、いままでと変わらなかった。
データ人間となったわたしは、人里離れた山中にある研究施設に置かれていた。
そこには「シャスター」のミラーコピーが収められたコンピュータがあり、きっとわたし以外の六人も同じ状況にあるのだろうと、連絡を取らずとも容易に想像が付いた。
劣化していく肉体から解放され、不老不死を得たわたしは、この無限にある時間を使って、わたしよりも完璧な “私のあの子” を造ろうと決心した。いまのわたしになら、母が感心し、涙するほど完璧な “私のあの子” が造れるはずだ。そう確信したわたしは、「シャスター」のミラーを管理しながらも、研究へと没入した。
ほどなくして、わたしは十三人の「妹」たちを造ることに成功する。
「ソル」を通じ、六人の妹たちを「アドミニストレータ」を守る役目につけ、他の六人を「シャスター」が創り上げた新世界を守る役目につけた。最後に、残りのひとり――
わたしの最高傑作を手元に残した。母もきっとこの子を見れば、“私のあの子” と区別が付かないだろう。
――そして、ブラックポイントが開いた。
わたしは繋がった並行過去世界で、“彼女” を見付けた。
「なぜ、“私のあの子” は死んだのに、この世界の “あの娘” は生きているの……」
都合がいいことに、“彼女” はリソース症候群で倒れ、入院している。わたしは “彼女” ……。かつてのわたしと同じ名を持つ、並行過去世界の “娘” の身体にナノマシンを仕込み、“娘” のデータを取ることにした。
“娘” の身体に仕込んだナノマシンからは、定期的に高濃度のリソースが噴出する。それを止めることができるのは、わたしが作った錠剤だけだ。
そして、わたしは “娘” を監視するためにひとりのクローンを遣わした。わたしの操り人形である彼女は、孤独な “娘” の友達として振る舞い、“娘” を守り、やがて “娘” の心を手に入れるだろう。
わたしの名前は、「アドミニストレータ ベガ」。
“あの娘” のデータを手に入れ、今度こそ完璧な “私のあの子” を造り出すのだ。